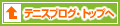2011年09月28日
世界で通用するテニス(改訂版)
クルム伊達は、日本人としては数少ない、世界の舞台で戦えるプレーヤーです。(でした、というのが正しいかもしれません。私が書いているのは、グラフと戦っていたころの伊達のことです。)クルム伊達のプレーについて、なぜ彼女が世界で通用するのか。
まず、クルム伊達について書く前に、Li Na(李娜)について考えてみたいと思います。二人とも、世界のトップに近い経験を持つアジア人女子プレーヤーです。
Na Liのフレンチオープン2011で書きましたが、私には、全仏オープン決勝のNa Liは、センターコートで、テニス発展途上であるアジア出身という宿命を背中に背負いながら欧米の歴史と戦っているように見えました。
しかし、その後、いろいろ調べてみると、Li Naはオープンでアメリカナイズされた個性(パーソナリティー)の持ち主だということが分かりました。(たとえば、李娜(Na Li)は復活できるか?をご覧ください。)Na Liは、アジアを代表するわけではなく、中国という国を背負うわけでもなく、一人のプレーヤーとして欧米のテニスの歴史に挑んでいたのです。
世界のテニスシーンで、これまでほとんど存在感を示したことがない中国(アジア)の女性プレーヤーが、なぜ、堂々と、グランドスラムの決勝で戦い抜くことができたのか?その理由の一つは、Na Liの良くも悪くも中国人女性らしくないといってもよいパーソナリティーにあるように、私には見えました。
Na Liのパーソナリティーについては、山口奈緒美さんのコラムでも、その明るくオープンなパーソナリティーがレポートされています。特に印象的なのは「アジアの常識を超えたパワーテニスに通じるリーのスケールの大きさを感じる」という部分です。私は、全仏オープン決勝の舞台でのNa Liからは、これまでのアジアのプレーヤーとは違うものを感じました。
これまで見てきたアジアプレーヤーは、大舞台において、どうやって自分をその舞台にマッチさせるかで苦しんできました。Na Liは、違いました。彼女は、試合の中で、自分の立ち位置を探し続けていました。欧米の長いテニスの歴史の中で、中国人として勝者になる絵を描こうとしていたのです。
中国のために戦うということと、中国人として戦うということは、全く意味が違います。この2つの違いが分からないから、いまだに多くのアジア人プレーヤーは、日本人プレーヤーは、世界のひのき舞台に立つことができないでいるのです。
さて、クルム伊達です。私は、プレースタイルも、年齢も、国籍も全く異なるこの二人に、どこか、共通の部分を感じています。
ウィンブルドン2011のクルム伊達対ウィリアムスの試合は、クルム伊達がまだ世界のトップと互角に戦えるということを示した試合だと評されています。しかし、私は、このゲームをテレビで観戦していて、別のことが気になりました。それは、ゲーム中に見せるクルム伊達の日本人女性独特のしぐさです。
たとえば、クルム伊達がミスをした時見せる「あ~」と言いながらしゃがみこむしぐさなどです。このような仕草は、全く、日本女性(女の子?)独特のしぐさです。下手をすると、「トップ選手なんだから、もっと堂々とした姿を見せてほしい」とは思う人もいるのではないでしょうか?
しかし、他人の目を気にすることなく、クルム伊達は、全く屈託なく、日本人っぽいジェスチャーや声、しぐさをコート上で見せます。そして、このことこそが、クルム伊達の強さの秘訣ではないのかと思いました。
日本人プレーヤーが、なぜ、世界のテニスシーンでトップまたはトップクラスになかなか躍り出ることができないのか。なぜ、クルム伊達は、当時、世界No.1のグラフに勝つことができたのに、他の日本人プレーヤーにはできないのか。
コート上での日本人っぽいジェスチャーが強さの理由だとは言いません。しかし、クルム伊達の強さは、他人の意見など気にもせずに、日本人らしさをウインブルドンのコートに平気で持ち込んでくるそのマイペースなスタンスに、理由の一つがあるのだと、私は思います。
日本人らしさを出すことが大切なのではありません。実際、クルム伊達も、よいポイントを取った時には、”Come on!”と英語で言ったりしています。すべてのアクションが日本人的なわけではありません。
日本人であることを、あるがままに、自然にコートに持ち込むこと。それができることが、クルム伊達の強さだと思うのです。テニス発展途上国である中国出身であることを楽しんでいるNa Liと、そこに、共通のものを感じます。
つまるところ、ルールなどなにもないのです。自分の中にしか。日本人の女の子っぽいしぐさも、思わず口に出る英語も、それが自分のモノであれば、他人の目など気にする必要はないのです。
一番大切なことは、自分の方法で自分を表現し、自分の方法で戦うこと。それができるかどうかが、世界の舞台で戦うことができるかどうかの大きな壁だと思います。
もちろん、国際社会(国際的なテニスの大会)においては、守るべきルールやマナーはあります。それらを破ってまで自己を貫くということは、国際社会では許されません。しかし、それ以外については、躊躇することなく、周りの目を気にすることなく、自分のやり方を貫けばよいのです。
一番よくないのは、他人の目を気にして、自分を出し切らない(出し切れない)ことです。案外、そういう選手が多いのではないでしょうか。特に、日本人は、協調ということを大切にすることを、子どものころから教育されています。そのことは素晴らしいことであり、日本の誇るべき社会文化だと思います。ただし、国際スポーツでは、それが裏目に出ることがあるのです。
選手がすべきことは、まずは、国際社会のルールの中でしてはいけないこととしなくてはならないことを分けて理解する。その基本ルールを十分に身に着けたら、今度は、それら以外については、他人の視線を一切気にせずに自分を出し切る。これが、国際的な大会で通用する秘訣だと思います。
選手のコーチや指導者、支援者がすべきことは、まだまだ、たくさんあるようです。
ただし、前提となることはあります。世界で通用するには、周りの視線を意識せずに自分のオリジナルなスタイルを貫くことですが、それは、あくまで、「貫くべき自分のスタイル」を確立できてからの話だということです。自分のスタイルがなくては、貫くモノもありません。
そして、自分の方法を、ゼロから作るのは難しいものです。「学ぶ」という言葉の語源は「真似をする(まねぶ)」ということだそうです。テニスに限らず、多くの技術は、真似をするところから始まるのです。
真似をするというのは、言い換えると、周りの影響を受けるということです。周りに影響を受けながら自分の方法を確立し、周りに影響を受けずに自分の方法を貫く。
この一見すると矛盾することを、あらゆるトップランナーたちは、行ってきました。これはテニスの世界だけの話ではありません。
そのタイミングの切り替わりはどこにあるのでしょうか。
おそらくそれは、オリジナル方法を真似し続けた結果、それが自分の体の一部になった瞬間だと思います。真似をするだけの対象は、おそらく完成度の高いものです。それを自らが取り込んだということは、いわば、自分は、その技術の後継者になったということです。
そこから先は、自分の道です。自分で切り開かねばなりません。
どこで、自分の道を歩き始めるのか。その判断ができるかどうかが、もしかしたら、いわゆる「一流」とう道を歩くかどうかの必要条件なのかもしれません。
まず、クルム伊達について書く前に、Li Na(李娜)について考えてみたいと思います。二人とも、世界のトップに近い経験を持つアジア人女子プレーヤーです。
Na Liのフレンチオープン2011で書きましたが、私には、全仏オープン決勝のNa Liは、センターコートで、テニス発展途上であるアジア出身という宿命を背中に背負いながら欧米の歴史と戦っているように見えました。
しかし、その後、いろいろ調べてみると、Li Naはオープンでアメリカナイズされた個性(パーソナリティー)の持ち主だということが分かりました。(たとえば、李娜(Na Li)は復活できるか?をご覧ください。)Na Liは、アジアを代表するわけではなく、中国という国を背負うわけでもなく、一人のプレーヤーとして欧米のテニスの歴史に挑んでいたのです。
世界のテニスシーンで、これまでほとんど存在感を示したことがない中国(アジア)の女性プレーヤーが、なぜ、堂々と、グランドスラムの決勝で戦い抜くことができたのか?その理由の一つは、Na Liの良くも悪くも中国人女性らしくないといってもよいパーソナリティーにあるように、私には見えました。
Na Liのパーソナリティーについては、山口奈緒美さんのコラムでも、その明るくオープンなパーソナリティーがレポートされています。特に印象的なのは「アジアの常識を超えたパワーテニスに通じるリーのスケールの大きさを感じる」という部分です。私は、全仏オープン決勝の舞台でのNa Liからは、これまでのアジアのプレーヤーとは違うものを感じました。
これまで見てきたアジアプレーヤーは、大舞台において、どうやって自分をその舞台にマッチさせるかで苦しんできました。Na Liは、違いました。彼女は、試合の中で、自分の立ち位置を探し続けていました。欧米の長いテニスの歴史の中で、中国人として勝者になる絵を描こうとしていたのです。
中国のために戦うということと、中国人として戦うということは、全く意味が違います。この2つの違いが分からないから、いまだに多くのアジア人プレーヤーは、日本人プレーヤーは、世界のひのき舞台に立つことができないでいるのです。
さて、クルム伊達です。私は、プレースタイルも、年齢も、国籍も全く異なるこの二人に、どこか、共通の部分を感じています。
ウィンブルドン2011のクルム伊達対ウィリアムスの試合は、クルム伊達がまだ世界のトップと互角に戦えるということを示した試合だと評されています。しかし、私は、このゲームをテレビで観戦していて、別のことが気になりました。それは、ゲーム中に見せるクルム伊達の日本人女性独特のしぐさです。
たとえば、クルム伊達がミスをした時見せる「あ~」と言いながらしゃがみこむしぐさなどです。このような仕草は、全く、日本女性(女の子?)独特のしぐさです。下手をすると、「トップ選手なんだから、もっと堂々とした姿を見せてほしい」とは思う人もいるのではないでしょうか?
しかし、他人の目を気にすることなく、クルム伊達は、全く屈託なく、日本人っぽいジェスチャーや声、しぐさをコート上で見せます。そして、このことこそが、クルム伊達の強さの秘訣ではないのかと思いました。
日本人プレーヤーが、なぜ、世界のテニスシーンでトップまたはトップクラスになかなか躍り出ることができないのか。なぜ、クルム伊達は、当時、世界No.1のグラフに勝つことができたのに、他の日本人プレーヤーにはできないのか。
コート上での日本人っぽいジェスチャーが強さの理由だとは言いません。しかし、クルム伊達の強さは、他人の意見など気にもせずに、日本人らしさをウインブルドンのコートに平気で持ち込んでくるそのマイペースなスタンスに、理由の一つがあるのだと、私は思います。
日本人らしさを出すことが大切なのではありません。実際、クルム伊達も、よいポイントを取った時には、”Come on!”と英語で言ったりしています。すべてのアクションが日本人的なわけではありません。
日本人であることを、あるがままに、自然にコートに持ち込むこと。それができることが、クルム伊達の強さだと思うのです。テニス発展途上国である中国出身であることを楽しんでいるNa Liと、そこに、共通のものを感じます。
つまるところ、ルールなどなにもないのです。自分の中にしか。日本人の女の子っぽいしぐさも、思わず口に出る英語も、それが自分のモノであれば、他人の目など気にする必要はないのです。
一番大切なことは、自分の方法で自分を表現し、自分の方法で戦うこと。それができるかどうかが、世界の舞台で戦うことができるかどうかの大きな壁だと思います。
もちろん、国際社会(国際的なテニスの大会)においては、守るべきルールやマナーはあります。それらを破ってまで自己を貫くということは、国際社会では許されません。しかし、それ以外については、躊躇することなく、周りの目を気にすることなく、自分のやり方を貫けばよいのです。
一番よくないのは、他人の目を気にして、自分を出し切らない(出し切れない)ことです。案外、そういう選手が多いのではないでしょうか。特に、日本人は、協調ということを大切にすることを、子どものころから教育されています。そのことは素晴らしいことであり、日本の誇るべき社会文化だと思います。ただし、国際スポーツでは、それが裏目に出ることがあるのです。
選手がすべきことは、まずは、国際社会のルールの中でしてはいけないこととしなくてはならないことを分けて理解する。その基本ルールを十分に身に着けたら、今度は、それら以外については、他人の視線を一切気にせずに自分を出し切る。これが、国際的な大会で通用する秘訣だと思います。
選手のコーチや指導者、支援者がすべきことは、まだまだ、たくさんあるようです。
ただし、前提となることはあります。世界で通用するには、周りの視線を意識せずに自分のオリジナルなスタイルを貫くことですが、それは、あくまで、「貫くべき自分のスタイル」を確立できてからの話だということです。自分のスタイルがなくては、貫くモノもありません。
そして、自分の方法を、ゼロから作るのは難しいものです。「学ぶ」という言葉の語源は「真似をする(まねぶ)」ということだそうです。テニスに限らず、多くの技術は、真似をするところから始まるのです。
真似をするというのは、言い換えると、周りの影響を受けるということです。周りに影響を受けながら自分の方法を確立し、周りに影響を受けずに自分の方法を貫く。
この一見すると矛盾することを、あらゆるトップランナーたちは、行ってきました。これはテニスの世界だけの話ではありません。
そのタイミングの切り替わりはどこにあるのでしょうか。
おそらくそれは、オリジナル方法を真似し続けた結果、それが自分の体の一部になった瞬間だと思います。真似をするだけの対象は、おそらく完成度の高いものです。それを自らが取り込んだということは、いわば、自分は、その技術の後継者になったということです。
そこから先は、自分の道です。自分で切り開かねばなりません。
どこで、自分の道を歩き始めるのか。その判断ができるかどうかが、もしかしたら、いわゆる「一流」とう道を歩くかどうかの必要条件なのかもしれません。